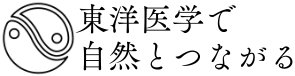2025年は3月5日から、二十四節気(にじゅうしせっき)の「啓蟄(けいちつ)」となります。
啓蟄とは、冬ごもりの虫たちが地中からはい出てくる“成長”の季節であり、私たち人間の心や体も変化しやすいとき。
そんな心身の変化を前向きなステップアップの力とできるように、東洋医学の知恵を使って養生していきましょう。
<次の節気>春分(しゅんぶん) 2025年3月20日~4月3日
<前の節気>雨水(うすい) 2025年2月18日~3月4日
啓蟄は、生命が殻を破って成長する季節

2025年は3月5日〜19日は、二十四節気(にじゅうしせっき)の「啓蟄(けいちつ)」です。啓の字には「閉じているものを開く」、蟄の字には「虫が地中に閉じこもる」という意味があり、啓蟄は「冬ごもりの虫たちが地中からはい出してくる季節」を表しています。
なぜこの時期に地中の虫たちがはい出してくるのかというと、日照時間が長くなって土が温まってくるため。啓蟄の日(3月5日)の日照時間は11時間34分(東京の場合)で、昼が夜と同じ長さになるまであと少しというところまで日脚が伸びてきています。
日照時間の長さは陽気(=太陽の熱エネルギー)の強さであり、陽気はすべての生物の熱源。啓蟄になるとこの陽気が地中まで届くようになり、その暖かさで虫たちが冬眠から目覚めるのです。
二十四節気をさらに細かく約5日ずつに区分けした七十二候(しちじゅうにこう)では、2025年の啓蟄は次のように季節が分けられています。
・3月5日~9日 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)……冬ごもりの虫が地上に出てくる季節
・10日~14日 桃始笑(ももはじめてさく)……桃の花がほころびはじめる季節
・15日~19日 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)……青虫が蝶に羽化する季節
冬ごもりの虫は巣穴から外へと飛び出し、桃はつぼみを開き、青虫はさなぎから抜け出て蝶になる。啓蟄は多くの生命が殻を破り、成長を遂げる季節といえます。私たち人間も、新しい世界に飛び出してステップアップしたくなる季節といえそうですね。
勢いよく日脚が伸び、陽気がどんどん強くなる

体のリズムを自然のリズムと調和させるためには、日の出の時間を意識して生活することがポイントです。理想的なのは日の出の時間に合わせて起きる生活ですが、それが難しい場合は日の出が早くなるのに合わせていつもより少し起床時間を早めるというように、日の出の時間の移り変わりを意識するだけでも自然のリズムに体が順応しやすくなります。
それでは、啓蟄の期間の日の出の時間をチェックしていきましょう。
以下の7都市では、啓蟄の15日間のうちに日の出が20~26分も早くなります。そして東日本の多くの場所では、啓蟄の期間中に日の出が5時台に突入します。それだけこの時期は勢いよく日が伸びて、陽気がどんどん強くなる季節ということ。この太陽の運行リズムのダイナミックな変化が、啓蟄の季節に生命が成長を遂げる原動力となっています。
◉啓蟄(2025年3月5日〜19日)の各都市の日の出の時間
| 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | ||
| 啓蟄 | 3月5日 | 6:04 | 6:03 | 6:06 | 6:17 | 6:22 | 6:34 | 6:42 |
| 3月6日 | 6:03 | 6:02 | 6:05 | 6:16 | 6:21 | 6:33 | 6:41 | |
| 3月7日 | 6:01 | 6:00 | 6:03 | 6:14 | 6:20 | 6:32 | 6:39 | |
| 3月8日 | 5:59 | 5:59 | 6:02 | 6:13 | 6:18 | 6:30 | 6:38 | |
| 3月9日 | 5:58 | 5:57 | 6:00 | 6:12 | 6:17 | 6:29 | 6:37 | |
| 3月10日 | 5:56 | 5:56 | 5:59 | 6:10 | 6:16 | 6:28 | 6:36 | |
| 3月11日 | 5:54 | 5:54 | 5:58 | 6:09 | 6:14 | 6:26 | 6:34 | |
| 3月12日 | 5:52 | 5:53 | 5:56 | 6:07 | 6:13 | 6:25 | 6:33 | |
| 3月13日 | 5:51 | 5:51 | 5:55 | 6:06 | 6:12 | 6:24 | 6:32 | |
| 3月14日 | 5:49 | 5:50 | 5:53 | 6:05 | 6:10 | 6:22 | 6:30 | |
| 3月15日 | 5:47 | 5:48 | 5:52 | 6:03 | 6:09 | 6:21 | 6:29 | |
| 3月16日 | 5:45 | 5:47 | 5:51 | 6:02 | 6:08 | 6:20 | 6:28 | |
| 3月17日 | 5:44 | 5:45 | 5:49 | 6:00 | 6:06 | 6:18 | 6:26 | |
| 3月18日 | 5:42 | 5:43 | 5:48 | 5:59 | 6:05 | 6:17 | 6:25 | |
| 3月19日 | 5:40 | 5:42 | 5:46 | 5:58 | 6:03 | 6:16 | 6:24 | |
なにかがうごめくような心身の不調には、余分な熱を静める養生を

冬ごもりの虫や蝶が、殻を破って羽ばたく……そんなふうに啓蟄とは、閉じこもっていた生命体が外へと飛び出し、エネルギーを発散する季節です。
私たち人間の体も同じように、春になると冬の間に体内に蓄えていたエネルギーを体の外へと発散しようと、上半身や体表面に向かってエネルギーをめぐらせていきます。
ところが、まだまだ寒暖差が激しいこの時期は、体を十分に開放しきれません。すると、外に発散したいのに発散できないエネルギーが体内で渋滞し、やがてそこに熱が生じて次のような不調が現れやすくなります。
頭部周辺の不調……顔が赤い、目が赤い、めまい、頭痛、耳鳴り など
精神面の不調……イライラする、怒りっぽい、不眠、夢をよく見る など
軽い熱感(熱があるわけではない)や心身の興奮をともなうのが特徴で、まるで心や体の内側でなにかがうごめくような不安定な状態になりやすいのです。
こうした不調を予防するために、啓蟄の季節は体内にたまりがちな余分な熱をおさえる養生に力を入れていきましょう。
「熱」タイプの不調には、肝にたまった熱を冷ます養生

この時期に起こりやすい熱感や心身の興奮をともなう不調は、大きくふたつのタイプに分かれます。
ひとつめは、長期のストレスなどが原因の「熱」タイプ。ストレスが強い状態でありながら十分な休息やリフレッシュができない状態が続くと、エネルギー(気)のめぐりが滞り、エネルギーをめぐらせる働きをになう五臓の肝(かん)に熱が生じる「肝火上炎(かんかじょうえん)」という状態になりやすい傾向があります。
「熱」タイプである肝火上炎は、主に次のような原因で起こる場合が多いです。
◉「熱」タイプ=肝火上炎の主な原因
・長期のストレス
・精神的な強い刺激、激しい感情の変化
・過度の飲酒や喫煙
・辛いものの食べすぎ など
肝火上炎は前述した頭部周辺の不調や精神面の不調のほかに、わき腹や肋骨部の熱感をともなう痛み、鼻血などの出血、口の中が苦い、口が乾く、便秘などの不調が見られる場合もあります。
「熱」タイプの肝火上炎を抑える、もしくは予防するためには、肝にたまった熱を冷ますことが養生のポイントとなります。次の食材は肝の熱を冷ます性質があるので、積極的にとってください。
◉肝にたまった熱を冷ます食材
トマト、ミント、しじみ、あさり、菊花茶、たんぽぽ茶
「乾」タイプの不調には、肝に潤い(水分)を補う養生

もうひとつのタイプは、肝の水分不足が原因の「乾」タイプ。肝を潤す体液や血液が不足し、水分不足による興奮状態が生じる「肝陽上亢(かんようじょうこう)」と呼ばれる状態です。「乾」タイプの肝陽上亢は、主に次のような原因で生じるケースが多く見られます。
◉「乾」タイプ=肝陽上亢の主な原因
・過労、過度の肉体労働
・夜ふかし
・老化
・セックスのしすぎ
・焦りすぎる、激怒するなどの極端な感情変化
肝陽上亢は前述した頭部周辺の不調や精神面の不調のほかに、もの忘れ、腰やひざがだるい、頭が重くて足元はふらつくなどの不調が見られることがあるのが特徴です。
「乾」タイプの肝陽上亢を抑える、もしくは予防するためには、肝に潤い(水分)を補うことで熱感や興奮状態を抑えることが養生のポイントです。次の食材は、肝に潤いを補う性質があるので、よくとるといいでしょう。
◉肝に潤いを補う食材
いちご、小松菜、かき(牡蠣)、ほたて、クコの実
啓蟄は成長の季節です。成長には変化がつきものであり、変化には不安定がつきもの。もぞもぞとなにかがうごめくような不安定さが感じられても、一皮むけてステップアップするプロセスだと前向きにとらえて、心身を安定させる養生をとり入れていきましょう。
画像素材:Adobe Stock、Envato