 季節と東洋医学
季節と東洋医学 【小寒(しょうかん)の自然と東洋医学】寒気が肌を刺す季節。「体を内側から熱する力」を高めよう
新年あけましておめでとうございます。冬至(とうじ)が過ぎ、年末年始が過ぎて、1月5日から二十四節気(にじゅうしせっき)の「小寒(しょうかん)」となりました。暦の上では晩冬、二十四節気もあと約1ヶ月で一巡します。小寒は「寒(かん)の入り」とも...
 季節と東洋医学
季節と東洋医学  季節と東洋医学
季節と東洋医学 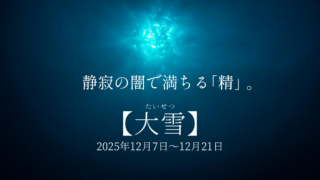 季節と東洋医学
季節と東洋医学  季節と東洋医学
季節と東洋医学  季節と東洋医学
季節と東洋医学 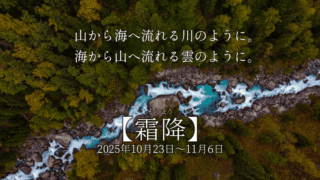 季節と東洋医学
季節と東洋医学 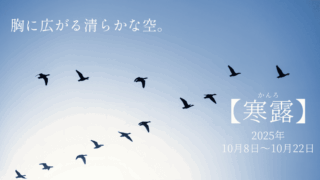 季節と東洋医学
季節と東洋医学  薬膳茶
薬膳茶  季節と東洋医学
季節と東洋医学  季節と東洋医学
季節と東洋医学