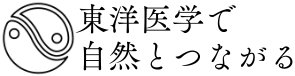3000年という長い年月をかけて体系化されてきた、中国起源の東洋医学。
体質改善によって自然治癒力を高めるのが特徴で、病気の人はもちろん、病名がわからない人や、病気ではないけれど健康かどうかわからないという未病(病気未満)の人にも対処できる医学です。
ここではその3つの魅力について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
東洋医学とは中国起源の経験的医学
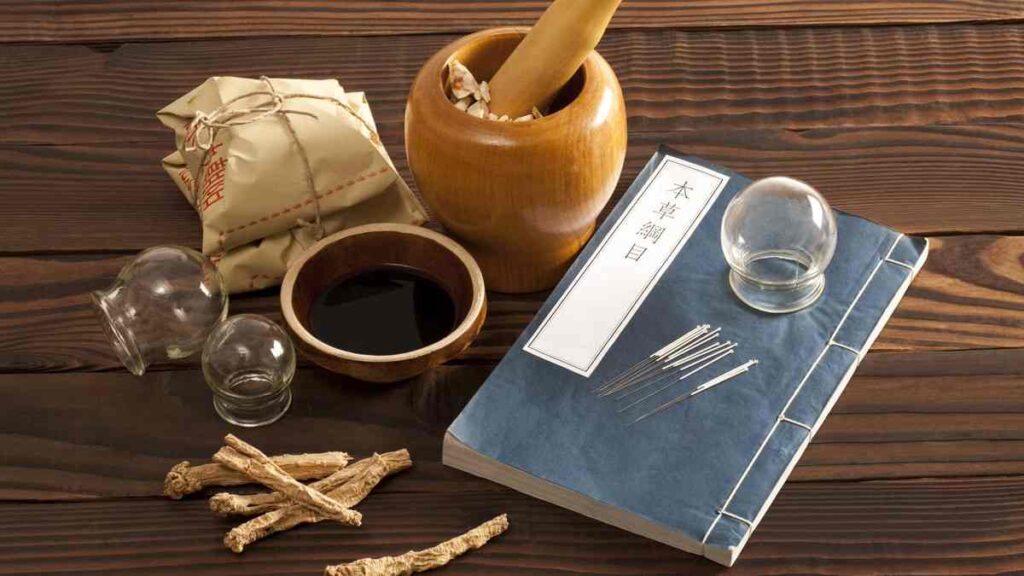
最近、テレビの特集などでも目にすることが多い東洋医学。
なかなか治らない自律神経系の不調やメンタルの不調、婦人科の不調なども、東洋医学なら改善できるかも……と、関心を持つ人が増えているようです。
でも、「そもそも東洋医学ってなんだろう?」と思う人も多いかもしれませんね。
東洋医学とは、一般的に2つの意味を持っています。ひとつは「アジア圏全体の伝統医学」をさし、日本や中国の伝統医学のほか、インドのアーユルベーダやヨガ、チベット医学などもこれに含まれます。
もうひとつの意味は、より範囲を絞った「中国起源の伝統医学」。漢方薬、薬膳、鍼灸(しんきゅう)、ツボ押しなどがよく知られていますね。
ここで取り上げる東洋医学とは、後者の「中国起源の伝統医学」と定義して話を進めていきます。
東洋医学は約3000年前の古代中国から始まり、中国や韓国、日本などで発展していった経験的医学です。
経験的医学とは、実際に施術してみて効果があった治療法だけが残り、効果がなかった治療法は淘汰されるという、臨床経験にもとづく医学のこと。3000年という長い年月をかけて膨大な治療経験が積み重ねられ、そこでふるいにかけられて、効果が認められた治療法だけが体系化されているのが東洋医学です。
東洋医学は西洋医学と比較されて「科学的根拠がない」といわれることがありますが、それは「理由はわからないけど効果があった」という経験も多く含まれる医学であるため。
しかし効果があったからこそ3000年間受け継がれてきたわけなので、信頼性はとても高く、実際に漢方薬を研究してみると治療効果が科学的にも裏づけられたという報告は大変多いのです。
そのため現在は、大半の医療用漢方薬が保険適用されています。
科学的研究から生まれ、そのあとに臨床経験が積み重ねられるのが西洋医学であるのに対し、臨床経験から生まれ、科学的解明が後追いになっているのが東洋医学。両者はそれぞれ得意分野が異なるので、現代では東洋医学と西洋医学、双方のいいとこ取りをすることがスタンダードになりつつあります。
・約3000年前の古代中国から始まり、中国や韓国、日本などで発展
・3000年という長い年月をかけて効果が認められた治療法だけが体系化されている経験的医学
・漢方薬の治療効果が科学的に認められた研究結果も多く、大半の医療用漢方薬が保険適用
・東洋医学と西洋医学、双方のいいとこ取りをすることが現代のスタンダード
東洋医学の魅力①「自然とつながる」医学(整体観念)

東洋医学の特徴として、「自然と人間はつながっている」という考え方があります。
「人間は自然の一部であり、自然と調和しながら変化している。そして人間の体内も自然と同じしくみで、さまざまな部位・組織・器官が有機的につながり合って一体となっている」
というもので、この考えは「整体観念」や「整体観」と呼ばれています。
人間は自然の一部であり、人間の中にも自然が息づいている
↓
朝昼夜、春夏秋冬といった自然界の営みに逆らった生活を送っていると体に不調が現れる
↓
心身を自然と調和するように整えると、不調が改善する
例えば不眠の原因のひとつに、体が潤い不足になり、相対的に熱が強くなって興奮状態になり眠れなくなるケースがあります。これはいわば、水不足によって大地が乾燥して気温が上昇するという異常気象が、体の中で起こっているようなもの。人間は自然の一部なので、自然界で見られる異常気象と似た現象が、体の中でも起こるわけです。
自然界の異常気象は環境汚染や森林破壊などが原因で起こりますが、体の中の異常気象の多くは、夜ふかし、過労、ストレスなど、自然界の営みに逆らった生活を送った結果生まれてきます。
自然界の異常気象を改善する場合は、大地を耕して水を与え、森を蘇らせて気温の上昇をやわらげるといった対策がとられます。
これと同様に東洋医学ではこのケースの場合、潤いが体内に吸収されるように胃腸を整え、潤いを補給して強すぎる熱を冷ますことで体の中の異常気象をやわらげて不眠の原因を改善します。この治療法は「滋水涵木(じすいかんもく)」といい、まさに水を補って木を潤すように治療をする、という意味なのです(「涵」は潤す、という意味)。
人間の体の中の自然を見つめて、そのバランスを整えることで不調を改善していく……これが東洋医学の大きな特徴であり、魅力といえるでしょう。
東洋医学の魅力② 体質改善をして症状の原因を根本治療

治療には大きく「症状を抑える治療」と「原因を治す治療」とがあります。例えば頭痛が起こった場合、鎮痛剤は“痛み”という症状を抑える治療になりますが、“痛み”の原因を治す治療ではないため、服用をやめると再び頭痛が現れる可能性があります。
東洋医学では「症状を抑える治療」だけでなく、症状の原因となる体質の改善を重視しています。
頭痛の場合なら、血行不良、むくみ、血液不足などさまざまな体質が原因として考えられるので、その体質を見極め、痛みを抑えるのと同時に体質改善をする薬が処方されます。体質改善することによって人間の体が本来持つ自然治癒力が高まるため、症状の原因を根本治療することができるのです。
なお、同じ頭痛であっても、血行不良が原因の場合とむくみが原因の場合では治療法が異なります。このように同じ症状でも原因となる体質の違いによって治療法がそれぞれ異なることを、東洋医学では「同病異治(どうびょういち)」と呼んでいます。
原因の違いに応じて治療法を変えることができるからこそ、一人ひとりにより最適な対処ができるわけです。
また、体質改善を行うと、体質が原因で生じていたほかの症状も同時に改善されることがあります。
例えば頭痛の原因が血行不良だった場合、血行不良を改善することで頭痛だけでなく血行不良による肌荒れや肩こりなども同時に軽くなる、ということがあります。根本治療ならではのメリットといえるでしょう。
このように違う症状でも、原因が同じであれば同じ治療法で同時に改善できることを「異病同治(いびょうどうち)」と呼びます。
◉同病異治……同じ症状でも、原因となる体質の違いによって治療法がそれぞれ異なること。一人ひとりの体質に合わせて最適な治療を行うという特徴を表している。
◉異病同治……原因が同じであれば、ひとつの治療で違う症状が同時に改善できること。
体質改善によって自然治癒力を高め、同病異治や異病同治が見られる場合があることも、東洋医学ならではの魅力なのです。
東洋医学の魅力③「未病」に対処する予防医学が得意
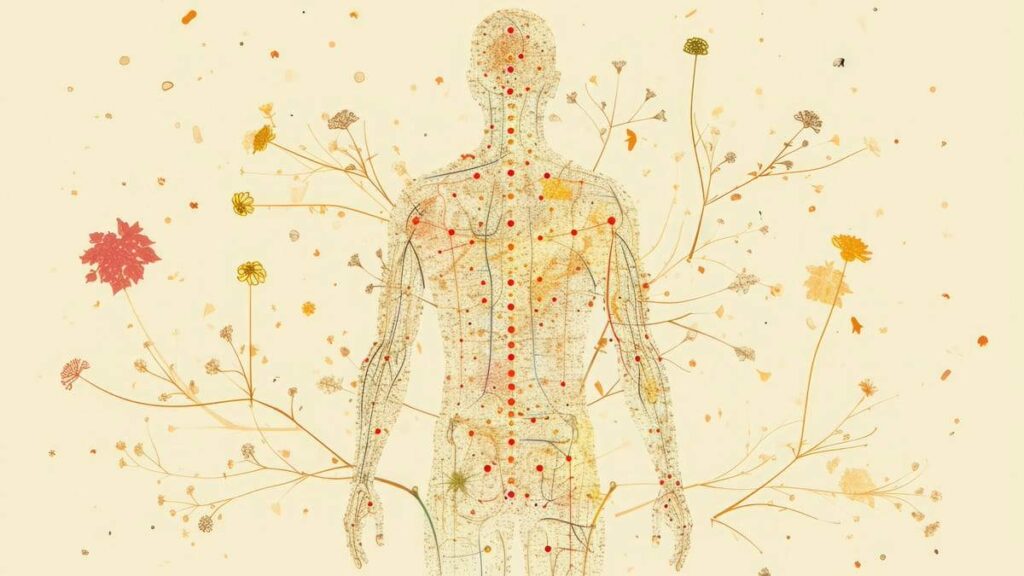
東洋医学は体質改善をめざす医学なので、診断についても“病名を診断する”のではなく“体質を診断する”という特徴があります。
東洋医学では、顔色、舌の色や状態、脈の強さや速さ、手足の冷たさや皮膚の状態、声の大きさやしゃべり方、呼吸の状態、食欲、睡眠、大小便の状態などを診察し、「証(しょう)」と呼ばれる体質名で診断されます。
そのため病気の人はもちろん、病名がわからない人や、病気ではないけれど健康かどうかわからないという未病(病気未満)の人でもなんらかの証が診断でき、治療や養生を行うことができるのです。
病気は基本的に、突然発症するものではありません。健康とは体や心が自然と調和している状態といえますが、その調和が崩れると、顔色が変わったり、肌が荒れたりといった体の変化が少しずつ見られるようになり、次第に変化が大きくなって食欲不振、だるさ、むくみ、冷えなどの未病となって現れてくるように。
それがやがて頭痛やめまいなどの症状となり、さらに進行すると深刻な病気に発展していく……というように、未病から徐々に病気へと変化していくのです。
健康=体や心が自然と調和している状態
↓
調和が崩れると、顔色が変わる、肌が荒れるなどの小さな体の変化が現れる
↓
進行すると食欲不振、だるさ、むくみ、冷えなどの未病に
↓
やがて頭痛やめまいなどの症状となり、さらに進行すると深刻な病気に発展
東洋医学には「名医は未病を治す」という言葉があります。これは、病気が発症してから治療をするのではなく、顔色の変化や肌の変化といったちょっとした異変を見つけ、未病の段階で適切な対処をして病気を防ぐ医師こそが名医であるという意味。
現代の日本では、顔色や肌の状態がちょっと変化したぐらいではなかなか医師に診てもらうことはないかもしれませんが、東洋医学の知識を身につければ、こうした小さな変化に自分自身で気づき、食事などの養生で病気を未然に防げるようにもなるでしょう。
東洋医学は、そうした未病を見つけるノウハウや、未病を改善するためのさまざまな養生法が充実しています。まさしく「予防医学を得意とする医学」というわけです。
人間の体を自然の一部として広い視点でとらえ、心身のバランスを整えて自然との調和をはかり、病気を防ぐ……これが、東洋医学のめざす医療と養生のあり方なのです。
画像素材:Adobe Stock、Envato