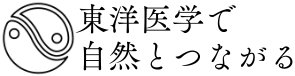2025年は2月3日から立春。江戸時代に発行された『こよみ便覧(べんらん)』には、立春について「春の気立つ」と説明されています。
「春の気」とは春の陽気のことであり、立春は地中にこもっていた陽気が地上へと立ち上がる季節。そして東洋医学では、私たち人間も立春を迎えると体の奥から陽気が上昇してくると考えます。
そこで、立春におすすめの陽気を体内にめぐらせる養生法をご紹介しましょう。
<次の節気>雨水(うすい) 2025年2月18日~3月4日
立春は春風が川の氷をとかし、その隙間から魚が跳ね上がる季節

天気予報などでよく耳にする二十四節気(にじゅうしせっき)。太陽の運行にもとづいて1年を約15日ずつ、24の節気に分けた暦で、立春はその二十四節気の最初の節気、春の最初の節気になります。
また立春は、旧暦のお正月にもあたります。まさに「新春」「迎春」ですね。
2025年の立春は2月3日〜17日で、そのはじまりである立春の日(2月3日)は、夜が最も長い冬至の日(2024年12月21日)と、昼と夜が同じ長さになる春分の日(2025年3月20日)の中間点となる日。
二十四節気をさらに細かく約5日ずつに区分けした七十二候(しちじゅうにこう)では、2025年の立春は次のように季節が分けられています。
・2月3日~7日 東風解凍(はるかぜこおりをとく)……東風(はるかぜ)が氷をとかす季節
・8日~12日 黄鶯睍睆(うぐいすなく)……うぐいすが鳴きはじめる季節
・13日~17日 魚上氷(うおこおりをいずる)……とけはじめた氷の間から魚が飛び跳ねる季節
やわらかな春風が氷をとかし、その風に乗って鳥の鳴き声が届き、冬の眠りから目覚めた川魚が薄氷(うすらい)の隙間から元気よく跳ね上がる……まさに春のはじまりの光景ですね。
ちなみに立春というと、一般的には立春のはじまりの日をさすことが多いのですが、厳密には次の節気(雨水=うすい)の前日までの約15日間のことも立春と呼びます。少しややこしいので、当ブログではその節気がはじまる日を「◯◯の日」、次の節気までの約15日間を節気名で呼んでいきます。
今回の場合は、
立春の日=2月3日
立春=2月3日〜17日
となります。
立春から太陽の勢いが加速を増してゆく

2025年の立春の日の日の出時刻は6:40、南中高度(1日で最も太陽が高くなる角度)は37.9度、日照時間は10時間31分です。
まだそこまで日の出は早くなく、太陽もあまり高くありませんね(データはいずれも東京の場合)。
ところがこの立春の日を境に、日の出の時間はどんどん早く、南中高度はどんどん高く、日脚もどんどん伸びていきます。
例えば、立春の約1ヶ月前の小寒(1月5日)の日の出時刻は6:51、南中高度は31.8度、日照時間は9時間51分で、その差は立春よりも日の出が11分遅く、南中高度は6.1度低く、日照時間は40分短いというもの。
一方、立春の約1ヶ月後の啓蟄(3月5日)の日の出時刻は6:06、南中高度は48.4度、日照時間は11時間34分で、その差は立春よりも日の出が34分早く、南中高度は10.5度高く、日照時間は1時間3分長くなっています。立春前の1ヶ月と比べて、数字の変化がかなり大きくなっているのがわかりますね。太陽の動きが加速を増しているのです。
◉[小寒→立春]と[立春→啓蟄]の太陽の動きの違い *( )内は立春との差
| 小寒[1月5日] | 立春[2月3日] | 啓蟄[3月5日] | |
| 日の出時刻 | 6:51(11分) | 6:40 | 6:06(34分) |
| 南中高度 | 31.8度(6.1度) | 37.9度 | 48.4度(10.5度) |
| 日照時間 | 9時間51分(40分) | 10時間31分 | 11時間34分(1時間3分) |
※データは2025年東京の場合
このように立春をすぎると太陽の動きがどんどん勢いづいていき、その勢いに乗って木の芽はふくらみはじめ、地中で新たな生命が目を覚ましてうごめき出したりと、春がどんどん色濃くなっていきます。
立春以降は、そんな太陽の勢いづく様子に注目していきたいですね。
日の出の時間に起きることを意識する

自然とつながるための最も重要な養生のひとつが、「日の出の時間に起きること」。太陽のリズムとともに生活することで、体も自然本来のリズムを取り戻し、活動と休息、覚醒と睡眠、エネルギーの燃焼と吸収など、あらゆる体のバランスが調和に近づいていくのです。
地域によって差がありますが、冬の間は日の出時刻がおよそ6時半~7時半の間で、それほど早い時間ではありませんでした。しかし立春以降はどんどん日の出が早くなるので、その勢いよく日が伸びてゆく春らしい変化を、毎日感じてみてはいかがでしょうか。
ゆっくり寝ていた冬の朝から、立春以降は少し早起きにシフトチェンジ。東日本は6:30頃、西日本は7:00頃を目安に、これまでよりも少し早起きをはじめてみてください。
そして朝起きたら窓を開けて朝日を浴び、新鮮な空気を深呼吸。新しい生命が地中でもぞもぞとうごめき出すように、私たちの体も冬の眠りから目覚めて、何か新しいことをはじめたくなったり自然と体を動かしたくなったりと体の中でうごめくものを感じられるかもしれませんよ。
体を冬モードから春モードへと切り替える、その第一歩を踏み出しましょう。
陽気を育て、上昇させ、発散させよう

太陽が勢いづいていくこの季節、体の中でも太陽の恵みである「陽気」が目覚めはじめます。
陽気とは太陽の熱エネルギー。自然界に存在するだけでなく、日光浴や光合成した野菜・穀類などを経由して、私たちの体の中にも取り入れられています。
冬の間、腰に位置する五臓の腎(じん)にじっくりと蓄えられた陽気は、立春を過ぎるとむくむくと目を覚まし、上昇しながら体を温めて、やがて体外へと発散されます。
外はまだまだ寒いのに、体を動かすと汗ばむのを感じる……立春以降のこうした体の変化は、まさに陽気の上昇と発散によるものなのです。
この陽気の成長・上昇・発散を食事で助けていきましょう。
おすすめはしょうが、ねぎ、みょうが、三つ葉、大葉などの薬味食材。これらは薬膳で「辛温解表類(しんおんげひょうるい)」と呼ばれ、辛味があって体を温め、発汗作用によって陽気の発散を促す特徴があります。これらの食材を温かい食事に少し多めに加えるだけで、立春にぴったりの薬膳メニューになりますよ。
また、体内の陽気を上昇・発散させるのは五臓の肝(かん)の働きも深く関係します。東洋医学における肝とは肝臓とイコールではなく、体内の気(き=エネルギー)をめぐらせる体の働きのこと。陽気も気の一種なので、肝の働きが重要なのです。
その肝による気をめぐらせる働きを助けるためには、かんきつ類をよくとるといいでしょう。ミントティー、ジャスミンティー、ローズティーなども肝による気をめぐらせる働きを促します。
そのほか、いい香りのものを身につけたり身の回りに置いたりすることも、気のめぐりをよくして肝の働きを助けます。ご自身の好きな香りを選ぶのがベストですが、ストレスが気になる場合は気のめぐりが悪くなりやすいので、グレープフルーツやスイートオレンジなどのかんきつ系のアロマを選ぶといいでしょう。
「立春は春風が氷をとかす季節」とご紹介しましたが、体の中でも陽気という温かい春風が吹きはじめます。この風が体の内側から外側へとスムーズに吹き抜けるように、養生をしていきましょう。
画像素材:Adobe Stock、Envato