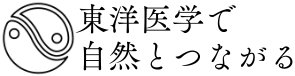2025年は2月18日から、二十四節気(にじゅうしせっき)の「雨水(うすい)」となります。
寒さが少しゆるんで雪が雨や水となることから、その名がついた雨水。
春の2番目の節気である雨水の時期に起こる体の変化は、春先に多く現れる頭痛、不眠、めまいなどの不調にも関わってきます。
不安定な春の体調を安定させるために大切なこの時期の養生法を、東洋医学の視点で解説していきます。
<次の節気>啓蟄(けいちつ) 2025年3月5日〜3月19日
<前の節気>立春(りっしゅん) 2025年2月3日〜2月17日
雨水は、春の芽吹きに欠かせない“恵みの雨”がもたらされる季節

雨水は二十四節気の2番目の節気で、春のはじまりである立春の次にやってくる節気です。
江戸時代に発行された暦の解説書である『こよみ便覧(べんらん)』には、雨水について「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されています。
陽気とは、太陽がもたらす熱エネルギーのこと。冬の間は地下にこもっていた陽気が立春を過ぎると地上へと上昇しはじめ、そしてこの時期になるとその陽気によって空から降る雪は雨に、積もっている雪は雪どけ水になって大地を潤すと考えられたことから、雨水と呼ばれるようになりました。
2025年の雨水は2月18日~3月4日。二十四節気をさらに細かく約5日ずつに区分けした七十二候(しちじゅうにこう)では、2025年の雨水は次のように季節が分けられています。
・2月18日〜22日 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)……土が潤いはじめる季節
・23日〜27日 霞始靆(かすみはじめてたなびく)……かすみがたなびきはじめる季節
・28日〜3月4日 草木萌動(そうもくめばえいずる)……草木が芽を出しはじめる季節
「土脉潤起」の「脉」は「脈」の別字。土に雪どけ水の水脈が湧き起こり潤ってゆく、そんな様子を表しているでしょうか。
土が雨や雪どけ水で潤い、その水分が気温の上昇とともに水蒸気となってかすみとなり、水を吸収した草木は芽吹きはじめる。
冴ゆる寒さが少しゆるんで、風がかすかに湿り気を帯びはじめる……三寒四温の季節ながらも、少しずつ、暖かい春へと進んでゆくのを感じられそうですね。
なお、この時期に降る雨は「木の芽起こしの雨」と呼ばれるのだとか。
ひと雨ごとに芽がふくらみ、成長をもたらすといわれています。
そして、この時期の雨や雪どけ水でぬかるんだ土は「春泥(しゅんでい)」と呼ばれ、新しい生命の脈動を象徴しています。
春は芽吹きの季節ですが、芽吹くために欠かせない“恵みの雨”がもたらされるのが、雨水の節気なのです。
日の出が毎日1~2分ずつ早くなっていく

2025年の雨水の日(2月18日)の日の出は6:25、南中高度(1日で最も太陽が高くなる角度)は42.8度、日照時間は11時間1分です。立春の日(2月3日)の日の出は6:40、南中高度は37.9度、日照時間は10時間31分だったので、だいぶ日の出が早くなり、日脚が伸びてきた感覚がありますね(データはいずれも東京の場合)。
以下は各都市の雨水の日の出の時間です。毎日1~2分ずつ、日の出が早くなっていきますね。日の出が遅い福岡でも、雨水の時期は日の出が6時台になっていきます。太陽のリズムが日々刻々と変化するのを感じ取れる季節です。
◉雨水(2025年2月18日~3月4日)の各都市の日の出の時間
| 札幌 | 仙台 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | ||
| 雨水 | 2月18日 | 6:28 | 6:23 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:52 | 7:00 |
| 2月19日 | 6:27 | 6:22 | 6:24 | 6:34 | 6:39 | 6:51 | 6:58 | |
| 2月20日 | 6:25 | 6:21 | 6:22 | 6:33 | 6:38 | 6:50 | 6:57 | |
| 2月21日 | 6:24 | 6:20 | 6:21 | 6:32 | 6:37 | 6:49 | 6:56 | |
| 2月22日 | 6:22 | 6:18 | 6:20 | 6:31 | 6:36 | 6:48 | 6:55 | |
| 2月23日 | 6:21 | 6:17 | 6:19 | 6:30 | 6:35 | 6:47 | 6:54 | |
| 2月24日 | 6:19 | 6:16 | 6:18 | 6:28 | 6:34 | 6:45 | 6:53 | |
| 2月25日 | 6:17 | 6:14 | 6:16 | 6:27 | 6:32 | 6:44 | 6:52 | |
| 2月26日 | 6:16 | 6:13 | 6:15 | 6:26 | 6:31 | 6:43 | 6:51 | |
| 2月27日 | 6:14 | 6:12 | 6:14 | 6:25 | 6:30 | 6:42 | 6:49 | |
| 2月28日 | 6:13 | 6:10 | 6:12 | 6:23 | 6:29 | 6:41 | 6:48 | |
| 3月1日 | 6:11 | 6:09 | 6:11 | 6:22 | 6:27 | 6:39 | 6:47 | |
| 3月2日 | 6:09 | 6:07 | 6:10 | 6:21 | 6:26 | 6:38 | 6:46 | |
| 3月3日 | 6:08 | 6:06 | 6:09 | 6:20 | 6:25 | 6:37 | 6:45 | |
| 3月4日 | 6:06 | 6:04 | 6:07 | 6:18 | 6:24 | 6:36 | 6:43 | |
体のリズムを自然のリズムと調和させるためには、日の出の時間に起きることが大切なポイントとなります。もちろんぴったりの時間に起きなくてもよくて、多少前後してもかまいません。おおよその日の出の時間に合わせて、起床時間を設定してみてください。
とはいえ、朝は苦手で日の出の時間に起きるのは難しい……という方もいらっしゃるでしょう。その場合も、日の出や日の入り、日の高さ、日照時間などの日々の変化を意識して生活するだけで、きっと自然とつながりやすくなるはずです。
体内における“恵みの雨”は「肝に血を補う」こと
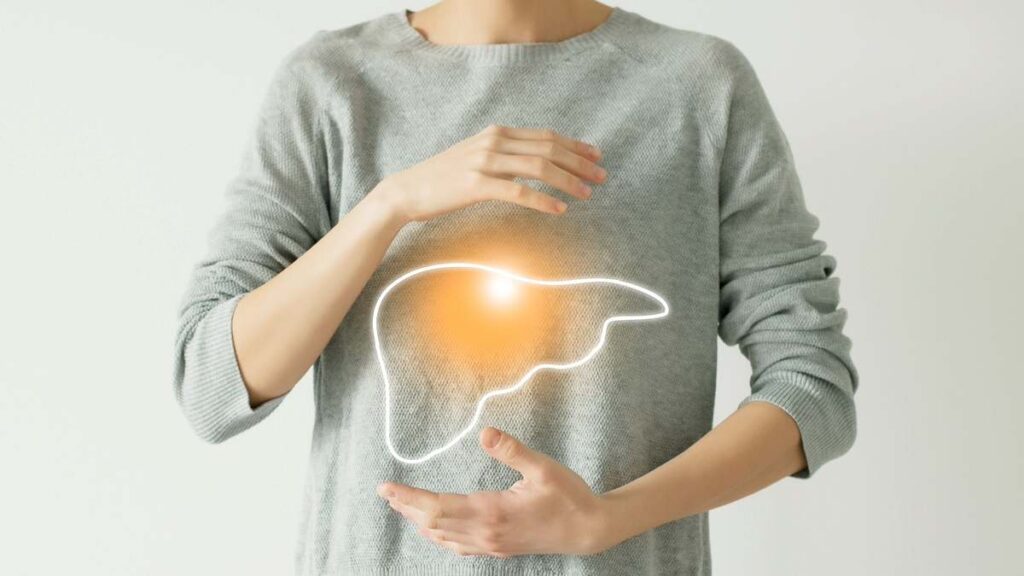
東洋医学では、春は自然界でも人間の体内でも「陽気が上昇・発散する季節」であると考えます。
自然界では、冬の間に地下にこもっていた陽気が春になると地上へと上昇・発散しはじめ、“芽吹きの力”となって草木の成長を押し上げていきます。
同じように人間の体も、冬の間に体内に蓄えられていた陽気が春になると上半身や体表面へと上昇しはじめ、体外へと発散されます。
そのため、立春以降は徐々に発汗しやすくなり、少し体を動かしたり温かいものを食べたりすると軽く汗ばむことが増えていきます。この陽気の上昇・発散によって、冬の間にたまっていた老廃物が排出され、代謝が高められていくのです。
こうした体内の陽気の上昇・発散は、五臓の肝(かん)による「疏泄(そせつ)」と呼ばれる働きがになっています。
疏泄とは体内の気(き=エネルギー)を上向き、外向きにめぐらせる働きのこと。「疏」の字には疎通するという意味、「泄」の字には排泄や発散などの意味があります。エネルギーを外向きに発散して体内の通りをよくする、というイメージですね。
肝の疏泄は一年中行われていますが、特に春にさかんになり、体の奥から陽気を上昇させて心身を冬の眠りから覚まし、伸びやかに活動させる力をもたらします。
まさに、体の中で起こる“芽吹きの力”ですね。
自然界では、草木の芽吹きには“恵みの雨”が欠かせませんでした。これと同じように、体の中の“芽吹きの力”である肝の疏泄にも、“恵みの雨”が必要となります。
肝にとっての“恵みの雨”は、血(けつ≒血液)。
肝の疏泄を正常に保つためには、肝に血を補うことが欠かせないのです。
自然界の草木に“恵みの雨”が与えられなければカラカラに枯れてしまうのと同様に、人間の体内でも肝に血が補われなければ、疏泄が異常になり、熱が生じてほてりやのぼせなどの不調を招いてしまいます。
雨水の時期はぜひ、肝に血を補う養生に力を入れていきましょう。
肝に血を補う雨水の食養生&生活養生

肝に血を補うには、食養生と生活養生のふたつの養生法があります。どちらも実践するのが理想的ですが、まずはできることからはじめてみてください。
①食養生:肝に血を補う食材をよくとる
ひとつめの養生法は、肝に血を補う食材をよくとることです。以下の食材はいずれも肝に血を補う性質に優れた、この時期におすすめの食材です。積極的にとっていきましょう。
・豚レバー……特に目の充血や視力低下、無月経、母乳不足などの改善に役立ちます。
・いか……特にめまい、けいれん、腰痛、おりもの、母乳不足などの改善に役立ちます。
・たこ……特に疲れ、息切れ、汗、めまい、月経不順、母乳不足などの改善に役立ちます。
・あわび……特に疲れ、熱感、不眠、母乳不足、視力低下などの改善に役立ちます。
・赤貝……特に筋肉のだるさ、手足のしびれなどの改善に役立ちます。
・ムール貝……特にめまい、寝汗、インポテンツ、おりもの、月経過多などの改善に役立ちます。
・黒ごま……特にめまい、ほてり、けいれん、乾燥肌、便秘などの改善に役立ちます。
・なつめ……特にめまい、イライラ・怒りやすい、月経不順、寝汗などの改善に役立ちます。
・くこの実……特にめまい、目の充血、視力低下、乾燥肌などの改善に役立ちます。
②生活養生:23時までに就寝する
肝に血を補うふたつめの養生法は、23時までに就寝することです。
日中に体内を循環している血は、睡眠時は肝へと戻ってきます。戻ってきた血は肝で解毒され、きれいな血となって肝に蓄えられ、翌日になると再び肝から血が体内を循環しはじめます。
この肝による血の解毒が行われるのが1〜3時。そしてその準備が23時からはじまります。そのため、23時までに就寝していると血がしっかり肝へと戻って解毒され、肝にきれいな血を蓄えることができるのです。
しかし23時以降も起きていると、肝に血が十分に戻らないため血が十分に解毒されず、肝の血も不足しやすい状態に。その結果、翌日はイライラしやすく、頭痛や目の充血なども起こりやすくなります。
そして、このような生活が長期的に続くと血が不足した体質となってしまい、めまい、不眠、視力低下、手足のしびれ・ふるえ、月経不順などが現れやすくなります。こうした不調を予防・改善するためにも、23時までに就寝することは大切な生活養生といえるでしょう。
春に働きがさかんになる肝に、“恵みの雨”をもたらす雨水の食養生と生活養生。不安定になりがちな春先の体調を安定させるためにも、ぜひ意識してみてください。
画像素材:Adobe Stock、PIXTA、Envato